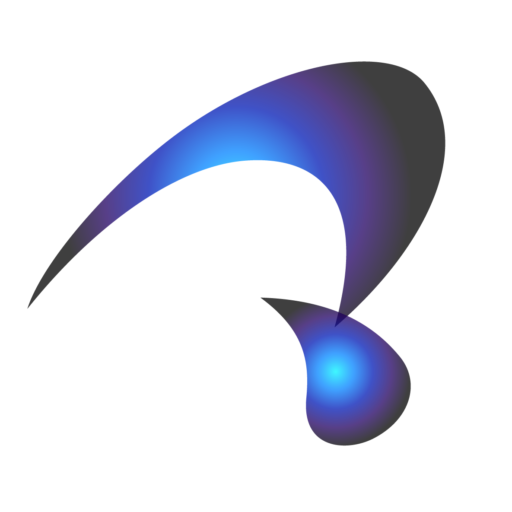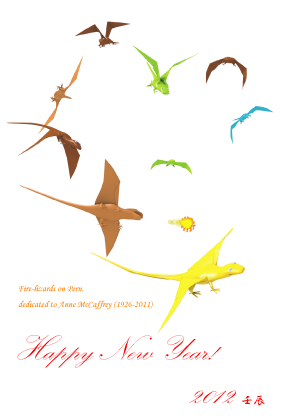朝日新聞「孤族の国」連載関連のリンク等
- 編集部のツイッター https://twitter.com/#!/asahi_kozoku
- asahi.com(朝日新聞社):孤族の国 – ニュース特集 http://www.asahi.com/special/kozoku/(第1部~第3部 一覧、webで読めます)
- 1-1: 55歳、軽自動車での最期 「孤族の国」男たち―1
- 1-2: 還暦、上海で婚活したが 「孤族の国」男たち―2
- 1-3: 失職、生きる力も消えた 「孤族の国」男たち―3
- 1-4: 39歳男性の餓死 「孤族の国」男たち―4
- 1-5: 彼は無表情だった 「孤族の国」男たち―5
- 1-6: 少女のような目の母と 「孤族の国」男たち―6
- 1-7: 聞いてもらうだけで 「孤族の国」男たち―7
- 1-8: 最後に人とつながった 「孤族の国」男たち―8
- 1-9: ひきこもり抜けたくて 「孤族の国」男たち―9
- 1-10: 自殺中継 ネットに衝撃 「孤族の国」男たち―10
- 1-11: 動かぬ体 細る指 外せぬ指輪「孤族の国」男たち―11
- 2-1: きずなを買う 「孤族の国」家族代行―1
- 2-2: 親孝行請けます 「孤族の国」家族代行―2
- 2-3: 子の送迎 救う手 「孤族の国」家族代行―3
- 2-4: ごみ・雪 公の出番 「孤族の国」家族代行―4
- 3-0: 震災 死悼む身内なし 「孤族の国」3・11から
- 3-1: 集落解散 消えるつながり 「孤族の国」3・11から―1
- 3-2: 細る開拓地 外国人妻涙 「孤族の国」3・11から―2
- 3-3: 避難の母 支えきれなくて 「孤族の国」3・11から―3
- 3-4: 心帰る場所流され「孤族の国」3・11から―4
- 3-5: 避難所出た途端、独り 「孤族の国」3・11から―5
- 「孤族の国」第4部「女たち」、朝日新聞 2011/12/9 p.1、2011/12/9・10・13・14・15の各p.37(社会面)。(紙またはオンライン有料)
- 4-0: 一面「単身女性の貧困3割強 20~64歳 母子世帯は57%」 2011/12/9 p.1
- 4-1: 「収入も伴侶もないままで」「置き去りにされる「家事手伝い」」 ( http://digital.asahi.com/articles/TKY201112080723.html) 2011/12/9 p.37
- 「TBS RADIO 小島慶子 キラ☆キラ: ポッドキャストバックナンバー」http://podcast.tbsradio.jp/kirakira/files/20120120_op.mp3 (http://www.tbsradio.jp/kirakira/pod/)
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=303149606397916&set=a.260233127356231.64525.257581560954721&type=1&theater
- 寒い日、熱き「ガールズトーク」に70人:公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 (フォーラム) http://www.women.city.yokohama.jp/find-from-c/c-minami/blog/1974.php
- 4-2: 「3人産んで みごとに独り」「若いつもりだったけど 孤独死の影」 2011/12/10 p.37
- 4-3: 「「幸せが待ってる」信じて」「母子家庭 困窮と暴力に追われ」 2011/12/13 p.37
- 4-4: 「「理想の家族」潜む孤独」「血縁あっても憎しみ悲しむ」 2011/12/14 p.37
- 4-5: 「人生支える緩やかな縁」 「地縁・血縁・会社縁を超えて」 2011/12/15 p.37
書籍化されるそうです。
朝日新聞は購読していないのですが…… 読みたいときのために題名等をメモしておきます。全体を通して高橋美佐子記者が関わり、第4部はキャップとのこと。
(2012/2/1)